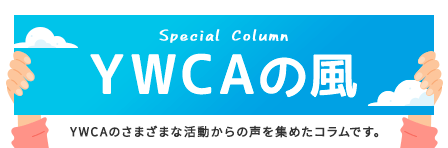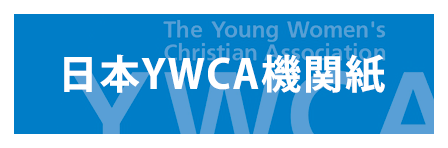憲法が示す平和とは:2つの戦場をつなげて考える

清末愛砂(憲法学者・室蘭工業大学大学院工学研究科教授)
「平和憲法」と呼ばれる理由
平和運動にかかわっていると、日本国憲法(以後、憲法)のことをあえて「平和憲法」と呼ぶ人々や団体によく出会います。そう呼ばれる主な理由は、憲法で特に①戦争や武力による威嚇、武力行使(宣戦布告などの戦意を示さずに武力を行使する事実上の戦争のこと)を放棄する9条1項と、②戦力の不保持や交戦権の否認を規定する同条2項が定められている点が高く評価されてきたからです。
帝国主義国家であった大日本帝国が引き起こした数々の武力行使(日本では一般に「戦争」と呼ばれる)により、国内外で多大な被害を生み出した歴史的背景に鑑みると、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにする
日本国憲法前文1段落
この決意を具体化する9条が規定されていることには、大きな意義があります。
最も重要な原理「基本的人権の尊重」
歴史的文脈から考えると、平和憲法という表現には理があるのですが、私はその意義を理解しつつも、使うことを控えてきました。その理由は、「平和」の意味が狭く使われていると考えてきたからです。平和運動で平和が唱えられるときには、歴史的背景を受けて、究極的な暴力である戦争や武力行使にかかわる問題が存在しないことを指すことが一般的です。しかし、平和と戦争を対置概念と位置付けた上で、憲法の三大原理の一つ「平和主義」が至上の原理であるかのように平和憲法と呼んでいくと、「基本的人権の尊重」が最重要原理であるという視点が抜け落ちてしまうことになりかねません。平和を広い概念で理解しようとするときに、基本的人権と平和が密接不可分な関係にあることがより明白になります。
あらゆる形態の暴力がないこと
では、憲法は平和をどのように考えているのでしょうか。「平和」という言葉は、前文では4か所、条文では9条1項で使われていますが、具体的な定義はなされていません。しかし、平和を脅かす要素として、前文2段落で「専制」「隷従」「圧迫」「偏狭」「恐怖」「欠乏」という言葉が言及されています。これらは、暴力をふるう主体が特定できる直接的暴力だけでなく、社会に存在する各種の差別や不公平に根差した構造的暴力を表すものです。つまり、禁止規定である9条1項が放棄する戦争や武力による威嚇、武力行使だけでなく、例えば、独裁体制、抑圧や圧迫を生み出す種々の権力関係(公私を問わない)、排外主義、貧困といった人権にかかわる幅広い形態の暴力を意味しています。憲法が前提とする平和とは、これらが根絶された状況を指すのでしょう。
「戦争」という戦場と日常生活にある戦場
現在の日本は、例えば、ウクライナやガザのように武力攻撃による被害者が多数出ている戦場ではありません。しかし、例えば、学校や職場で、あるいは家族のような親密圏で、権力関係に起因するハラスメントやいじめ、DVや児童虐待のようなファミリー・バイオレンスの被害に苦しんでいる人々がいます。これらの人々にとってみれば、日常生活はけっして平和なものではなく、加害者がいる学校や職場、家族は戦場ともいえる場なのです。平和を考えるときには、こうした2つの戦場があることを認識すると共に、両者に共通するものは何か、いかなる形で結びついているのかといった点を精査することが求められます。
平和を脅かすものから解放される権利
ここまで読むと、平和とは前述のように「状態」を表すものに思えるかもしれません。しかし、実は「権利」という側面も持っているのです。憲法前文には、「平和のうちに生存する権利」(平和的生存権)が謳われています。前述の「恐怖」や「欠乏」は、この平和的生存権を構成する鍵となる言葉として言及されているのです。簡単に書くと、これらから解放される権利ということになります。(ただし、司法は平和的生存権を抽象的権利としてみなす傾向が強いため、違憲訴訟では平和的生存権の侵害がなかなか認定されない)。もう一つの特徴は、全世界の人々を対象とする権利とされていること。この点は、前述の二つの戦場の関係性を考える際に、大きな示唆を与えるものとして頭に入れておく必要があるでしょう。なお、平和の権利性に関しては、2016年12月19日に国連総会で採択された「国連平和への権利宣言」1条でも確認されています。
【プロフィール】
清末愛砂(きよすえ・あいさ)
1972年生まれ。山口県出身。大阪大学大学院助手、同助教、島根大学講師を経て、2011年10月に室蘭工業大学大学院准教授として着任。21年6月から同教授。専門は憲法学(特に平和主義から考える24条の意義)、ジェンダー法学、アフガニスタンのジェンダーに基づく暴力。著書に『平和に生きる権利は国境を超える パレスチナとアフガニスタンにかかわって』(共著、あけび書房、2023年)など多数。